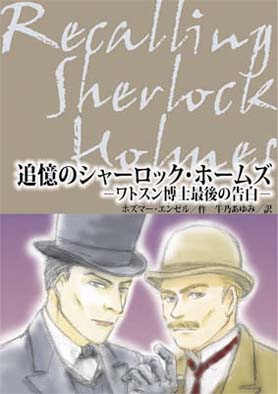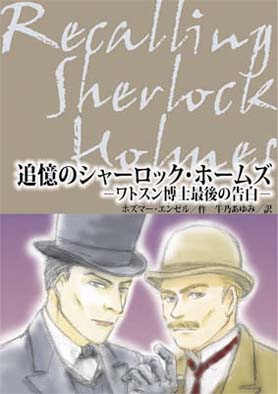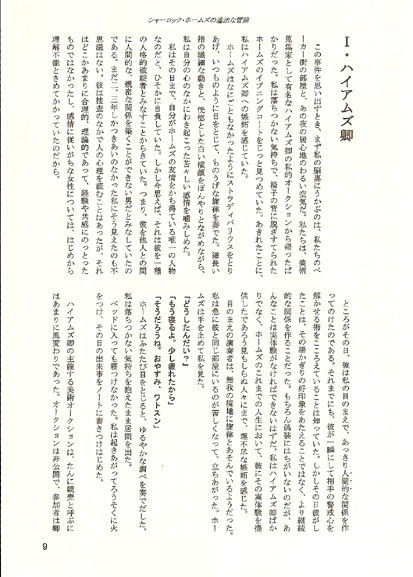Ⅰ・ハイアムズ卿
この事件を思い出すとき、まず私の脳裏にうかぶのは、私たちのベーカー街の部屋と、あの夜の居心地のわるい空気だ。私たちは、美術蒐集家として有名なハイアムズ卿の私的オークションから帰ったばかりだった。私は落ちつかない気持ちで、椅子の背に脱ぎすてられたホームズのフロックコートをじっと見つめていた。あきれたことに、私はハイアムズ卿への嫉妬を感じていた。
ホームズはなにごともなかったようにストラディバリウスを取りあげ、いつものように目をとじて、ものうげな旋律を奏でた。細長い指の繊細な動きと、恍惚とした白い横顔をぼんやりとながめながら、私は自分の心の中にわき起こった苦々しい感情を噛みしめた。
私はその日まで、自分がホームズの友情をかち得ている唯一の人物なのだと、ひそかに自負していた。しかし今思えば、それは彼を一種の人格的破綻者とみなすことからきていた。つまり、彼を他人との間に人間的な、親密な関係を築くことができない男だとみなしていたのである。まだ二、三年しかつきあいのなかった私にそう見えたのも不思議はない。彼は捜査の中で人の心理を読むことはあったが、それはどこかあまりに合理的、理論的であって、経験や共感にのっとったものではなかったし、感情に従いがちな女性については、はじめから理解不能ときめてかかっていたのだから。
ところがその日、彼は私の目のまえで、あっさり“人間的”な関係を作ってのけたのである。それまでにも、彼が一瞬にして相手の警戒心を解かせる術を心得ているのは知っていた。しかしその日彼がしたことは、その場かぎりの好印象をあたえることではなく、より継続的な関係を作ることだった。もちろん偽装にはちがいないのだが、あんなことは実体験がなければできないはずだ。私はハイアムズ卿ばかりでなく、ホームズのこれまでの人生において、彼にその実体験を提供したであろう見もしらぬ人々にまで、理不尽な嫉妬を感じた。
目のまえの演奏者は、無我の境地に旋律とあそんでいるようだった。私は急に彼と同じ部屋にいるのが苦しくなって、立ちあがった。ホームズは手を止めて私を見た。
「どうしたんだい?」
「もう寝るよ。少し疲れたから」
「そうだろうね。おやすみ、ワトスン」
ホームズはふたたび目をとじると、ゆるやかな調べを奏でだした。私は落ちつかない気持ちを抱えたまま居間を出た。
寝床に入っても寝つけなかった。私は起きあがってランプをつけ、その日の出来事をノートに書きつけはじめた。
ハイアムズ卿の主催する美術オークションは、たんに競売と呼ぶにはあまりに風変わりであった。オークションは非公開で、参加者は卿が招待状を送付したいくつかの、その嗜好において多少悪名たかいクラブの会員たちと、その同伴者だけであった。
オークション会場となったのは、郊外の青柳館という広大な屋敷で、もちろんハイアムズ卿の住まいである。年代を感じさせる、美しい蔦におおわれた館は、ゆるやかな丘の頂上を占めるようにそびえ建っており、まわりを守るように落葉樹の森が広がっている。門から入ると最初に見える母屋は、玄関のホールをはさんで東西に分かれており、さらに裏手には木立をへだてて棟がふたつあった。こちらにはあるじ自慢の古武器や骨董などのコレクションがあり、おもに趣味のために使われていた。その日はもちろん来客に開放されて、紋章の入った古い楯や石弓にまじって、冗談らしく陳列されたエドワード二世の冠だの、聖剣エクスカリバーだのが皆の目を楽しませた。裏庭には植えこみを刈りこんで作った迷路があり、さらに下っていくと葦の生えた池があった。その岸の一角に、館の由来となった柳の大木が立っていた。
ハイアムズ卿は、べつに経済的理由から手持ちの美術品を売っているわけではない。同好の士との交遊の場としてそのオークションを催しており、そのために年に数回、大陸へ美術品の買い付けに行っていた。気にいったものは手元におきたくなりそうなものだが、卿は仲間とそれを分けあうことを好み、たとえ売上げが投資に見あわずとも…常にそうだったらしいのだが…気にしなかったという。卿と親交のあついメルピット氏という競売人を立て、いちおう競売の体裁はととのえていたものの、いうなれば一種のサロンであった。なんとも金のかかる道楽である。
ホームズはそのころ、メサイアの瞳という宝石の盗難事件を追っていた。その捜査線上にハイアムズ卿の名がうかび、その日の潜入とあいなったわけである。ホームズが裏でどう手をまわしたのかは知らないが、私たちはとある子爵とその友人として青柳館にまぎれこんでいた。
その日のホームズは黒い髪を粋になでつけ、アスコット・タイに異国風のピン、日ごろの彼なら鼻で笑うような華やかな織り模様の入ったチョッキなどを身に着けて、いっぱしのしゃれ者貴族と化していた。青白い顔にも薄く化粧をほどこしていたので、私と並ぶと十(とお)も年が離れているように見えた。
カタログに記載された品々は、この広い邸内ぜんたいにわたって趣向をこらして展示され、値付け人たちは午前中いっぱいかけて下見を楽しんだ。
その趣向は、たとえばキリスト生誕の絵には三賢人に扮した役者を配し、天使の絵は背中に羽根をつけた半裸の少年たちにかかげさせるという具合で、各部屋の装飾も展示品の主題に合わせてあり、展示自体が見せものとなっているのだった。どことなく退廃的なものばかりで私の趣味には合わなかったが、ホームズは判じ物を読み解くように、面白そうに見いっていた。
競売品の下見がおわると、庭園で豪華な昼食が饗された。午後にはギリシャ風の衣装をつけた美しい青年たちが、庭に好き勝手に散らばった客たちに飲み物をはこんだ。ようやく競売がはじまったのは午後三時であった。
あつかわれたのは絵画がほとんどだが、彫像や宝石もいくつかあった。ホームズは出てきた美術品や宝石の来歴を、いちいち私に耳打ちした。彼は二、三の品の値をつり上げるのに一役買い、結局はひとつも競りおとさなかった。彼は競り負けるとあからさまにくやしそうな顔をし、めったにしない舌打ちまでしてみせた。
競売がおわり、彫刻で飾られた広間に出た私たちは、葉巻をやりながら、着飾った紳士淑女の群れをながめた。私は少しからかうように言った。
「ホームズ、ひとつも競りおとせなかったじゃないか」
「競りおとすのが目的ではないよ。これでいいのさ。ハイアムズ卿を見たかい?彼は僕に目をつけたぜ。あのちょっとした演技で、僕は美術品に目がなく、熱心だが少々手元不如意な貴族の息子ってあたりに見られたはずだ。必ずあちらから声をかけてくるよ」
「そううまくいくかな」
「いくさ。僕が競りに加わったものがなんだったか覚えているかい?」
「全部絵だったけれど…」
「オランダ絵画だよ。つまりハイアムズ卿とぴったり趣味の合う若造というわけさ」
葉巻を吸い終わらないうちに、ホームズの言ったとおり、ハイアムズ卿が声をかけてきた。
「お楽しみいただけましたか?」
ホームズは、それ見たことかと言わんばかりにちらりと私を見た。
・・・ |