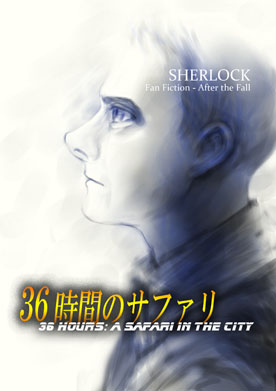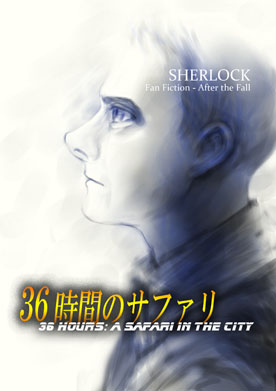36時間のサファリ
Act 1
『吐きだせ』
第一声はこれだった。もっとも、ジョンの耳には入っていなかった。目にしたものが他の感覚を奪ってしまったのだ。
死んだはずの男が、その頃の姿のまま、部屋のドアを蹴り開けた。まだ暖かい秋の始めなのに、男は厚手の黒っぽいコートを着ている。
それと同時に、焼けるような感覚が胃に走った。テーブルには手をつけたばかりのサンドイッチとお茶があったが、たまらずそのうえに突っ伏した。男はテーブルにつかつかと歩み寄ると、ジョンをテーブルから持ち上げて口に指を入れた。
『吐くんだ』
食べたばかりの朝食が、食べていない朝食をだいなしにした。ジョンは男の手を振りきって見上げたまま硬直した。悪寒がして全身がふるえた。見ているものが信じられなかった。男はジョンに向かって何かどなっている。
「シャーロック」
ジョンはそうつぶやいて昏倒した。
―――――――――――――――
軍医の仕事は、外傷の手当ばかりではない。
自殺をはかった兵士に、ジョンは何度か胃洗浄の処置をしたことがあった。そういう場合のルーティンだ。とりわけ患者に意識がなく、飲み込んだものを確認できない場合には、唯一の選択肢といえた。手順も安全性も知っている。
だが、自分がやられるのはもうごめんだ。そう思いながら、ジョンは目を開けた。知った顔が見下ろしていた。
マイクロフト・ホームズ。彼の弟の死後は一度しか会っていない。ジョンはまばたきして言った。
「…食中毒じゃない」
マイクロフトは首をかしげた。
「なんだと思う?」
「何かの実験?諜報部が開発したものでも試した?」
「なぜそう思う」
「あんたがここにいるから…」
「そんなことはしない」
「していてもそう言う」
マイクロフトは目つきをそのままに、口の端だけ持ち上げた。
「私の素性を知っている者にそんなことをして、直後に会いにくるほど馬鹿じゃない」
「ありがたいね…じゃあなんでここにいる?」
「通報があったんだ。状況を聞かせてほしい。…なぜ食中毒じゃないとわかる?」
「もう『中身』を調べたんだろ?」
「胃にはほとんど何も残っていなかったよ。吐物と残りのサンドイッチと紅茶を分析させているが、まだ結果は出ていない。念のため君が朝食を買った店には保健所の者をやる」
マイクロフトは店の袋を持ち上げて見せた。電話番号が入っているから、なんの手間もない。家族経営の小さな店で、いつも店番をしている老婆とは顔なじみだ。太っていて愛想がいい。ジョンは首を振った。
「保健所の管轄じゃないよ。食中毒で幻覚なんか見ない。誰かが何か入れたとしか…」
マイクロフトは眉をしかめた。
「幻覚?」
ジョンは部屋を見回して初めて気付き、がばっと起きあがった。
「ここはどこだ?」
「…君の部屋は危険になった。ジョン」
その部屋は広かった。ベイカー街を引き払ってから住んでいる部屋の数倍はある。病院でもなかった。くすんだえんじ色の壁紙は上品だが古くさく、窓がない。家具も立派だが少ない。
ドアから執事の服装をした老人が現れ、銀のティーセットを乗せた盆を重そうに運んできた。マイクロフトはサイドテーブルの横に座り、ティーポットからお茶を注ぎ始めた。
「君には聞くことがある」
「聞くのはこっちが先だ。通報っていったい誰が…」
「悪いが今は答えられない。こちらの用件は…」
「国家の大事(ナショナル・インポータンス)?あんたの仕事に僕を巻き込むな。もう…」
ジョンは一瞬口をつぐんだ。
「…彼はいないんだから。僕はただの失業中の医者だ」
「失業中の医者が必要なんだ」
マイクロフトはお茶を乗せた皿を差しだした。ジョンはそれを取ってサイドテーブルにがちゃんと置くと、ベッドから立って部屋を見回した。隅にある椅子に上着と靴があった。下着やシャツもいくつか。部屋から持ち出されたらしい。ジョンは上着のポケットに入っていた財布の中身を確認した。
「ここでしばらく過ごすんだ。君の部屋には戻るな」
「なぜ」
「…聞かないでくれ」
ジョンはフン、と鼻を鳴らすと靴を履いた。
「泊まり込むなら、シーツとピローケースがいる」
「ばかな。必要なものはある。何が不満だ」
マイクロフトは両手を広げた。部屋は天井が高く、ツタ模様の入った重厚なコーニス(天井と壁の交差部の装飾)がぐるりと囲んでいる。大きなベッドにはご丁寧に天蓋まである。ジョンは応えるように両手を広げた。
「シルクは寝心地が悪い」
そう言い捨てると、上着をつかんでドアを開けた。
廊下を歩き回り、場所の見当はついた。高級で落ち着いた調度。この静けさ。窓辺の椅子に座って新聞を読む、気むずかしそうな男たち。そこら中に人がいるのに、音を立てている者は一人もいない。
ディオゲネス・クラブ。玄関を出ればペル・メル街だ。
―――――――――――――――
外は晴れていて、ここ数日では珍しいほど明るい日が差していた。ジョンは胃のあたりに手をあてた。不快感はなくなっている。問題なし。
とにかく動きたかった。そして頭を整理したかった。少なくとも、何か考えられる程度に。じっとしていたら気が狂いそうだ。
歩き続けてペル・メル街から右に折れ、セント・ジェームズ・ストリートへ入った。人通りはほとんどなく、車道もがら空きで、歩道に沿って縦列駐車ばかりが目立つ。通りをしばらく進むと、ジョンの携帯が鳴った。ジョンはうんざりしたように首を振って、携帯をポケットからとり出した。相手は名乗らずに切り出した。
「今どこにいる?」
「わかってるのになぜ聞く」
ジョンは通りの向こう側の若いカップルを横目で見た。人がいないだけに目立った。こちらが立ち止まると、あちらも止まっていちゃつき始める。マイクロフトが電話の向こうでため息をついた。
「…こちらが聞きたい。わかっているのに、なぜ時間を無駄にする」
「バカなもんでね」
「私が相手だからか」
「そうかもしれない。信用できない」
「なぜ」
「なぜ?よく聞けるな。自分の弟を助けなかった…」
「私にできることは何もなかったんだ」
ジョンは一呼吸おくと、声をひそめて言った。
「あんたなら何でもできたはずだ」
「…今はその話はやめよう」
マイクロフトはほんの少し沈黙した。手元のコンピューターを操作している。
「…最後に雇用されたのは二ヶ月前だな。職がほしいなら…」
「あんたの世話になるくらいならホームレスになる」
「ジョン、言い争っている暇はない」
「目隠しして引き回すようなまねはやめろ」
「…わかってくれ。私の一存では明かせないんだ」
「じゃあ、あんたの上司にこう伝えろ。僕はあんたの部下じゃない」
「ジョン…」
ジョンは前方を見て立ち止まった。電話のむこうでマイクロフトが誰かと話している。
「ジョン。そこで止まれ」
「止まってる」
「見えるのか」
「ああ」
横道から出てきた二人連れの男が、こちらへ向かって歩いてくる。一人は古着のようなレザーのジャケットを着ている大男。もう一人は中背でデニムシャツにコーデュロイのパンツ。二人ともはっきりとこちらを見ている。
…通りの向こうの「カップル」が、もし追跡対象を守る任務を帯びているなら、むろん武装しているはずだ。だが、やけに多い駐車の列が切れ切れに邪魔をしている。通りを横切って駆けつけるのでは間に合うかどうか…。いつも引き出しに入れている拳銃が今あれば。マイクロフトは「危険」と口にしていなかったか。見越していたなら、どうしてあれを上着のポケットに入れておいてくれなかったんだ…ジョンは電話を握りしめた。
… |