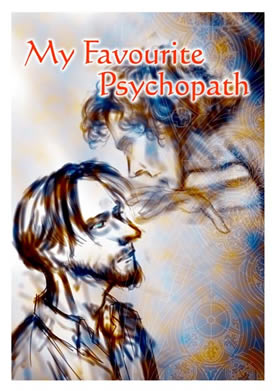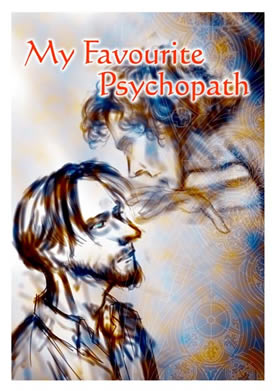My Favourite Psychopath
「ほら、これは僕一人が思ってることじゃない…世界中で言われてるんです」
アンダーソンは自室のデスクの上でノートパソコンを開いて見せた。レストレード警部はコートのポケットに手をつっこんだまま、画面をちらりと見て眉をしかめた。そしてアンダーソンの顔に視線を戻した。アンダーソンは確信に満ちた目で見返した。無精ひげが生えている。いつも几帳面に剃っていた男が。…部屋に入るんじゃなかった、と警部は後悔した。
夜明け前、アンダーソンが警部の携帯に電話をよこしたとき、警部はジョンの部屋にいた。ジョンなら彼を説得できると考え、ジョンを連れて早朝の定食屋で落ち合うことにした。いまだにジョンとつながりがあることなど詮索されたくなかったが、今のアンダーソンは関心を示さないだろうと予想した。実際その通りだった。今の彼は、ある問題以外まったく眼中にない。
…ジョンを連れて行ったことも、今では後悔していた。どうして辛い思いをさせると気づかなかったのか。あたりまえじゃないか。アンダーソンは、シャーロックを追いつめた張本人なのだ。…だが最近落ち着きを見せているジョンよりも、あきらかにおかしくなってきている鑑識官のほうが気がかりだった。それでジョンが助けになるなどと、軽々しく考えてしまったのだ。
アンダーソンは、目の前でシャーロックの死を目撃した親友の言葉も聞き入れなかった。ジョンと別れて店を出ると、警部の耳元で「彼もグルにきまってます」とささやいた。警部の不安は大きくなり、とりあえず一日仕事を休むよう言い伏せ、念のため家まで送ってきた。途中おかしなことをしかねないと思ったのだ。
アンダーソンは道々彼の「疑い」を警部に説いた。ときどき往来なのを忘れたように大声をだし、警部は好奇の目を浴びながら、気まずい思いで彼をひきずってきた。
ようやく家に着き、ドアの前で警部が帰ろうとしたとき、アンダーソンの携帯の着信音がした。メールは、彼がチェックしているサイトのアップデートを知らせるものだった。彼は警部をむりやり引きとめ、「証拠を見せる」と言った。
しぶしぶなかに入った警部は、アンダーソンの妻がいないことにすぐに気づいた。昨日や今日いなくなったわけではないことが、室内の様子から知れた。
パソコンの画面はインターネット上の掲示板で、上部に
『シャーロック・ホームズは生きている』
と書かれていた。目撃談らしきものや、それぞれの「推理」が書き込まれているらしい。
「新しい書き込みです…証拠だと思いませんか」
「こんなものがなんの証拠になるんだ!」
最新の書き込みを見て、警部はうんざりした声をあげた。
『昨夜あたしの部屋に泊まっていったの。彼は思ったより上手で……』
写真が付いていて、鹿撃帽をかぶった若い裸の女が、胸を手で隠して微笑んでいる。文末には別サイトへのリンクがついていた。さぞや上品なウェブサイトにつながっているんだろう。
「…ただの悪趣味な『釣り』だ」
「よく見てください。アメリカの娘じゃないですか…彼が行ってないとしたら、どうして彼のことなんか知ってるんです?国内では知られてるが彼は……」
警部は勘弁してくれというように大声を出した。
「本気にしてるのか?地名なんかなんとでも書けるだろ!」
「わかってます、それくらいわかりますよ…こんなものは無視して…」
アンダーソンは両手を上げてうなずきながら言った。
「…たしかにほとんどの書き込みはでたらめだ。でもこういうサイトはほかに四つあるんです。その中にほんの一握り、真実も埋もれてる可能性がないとは……」
「――アンダーソン」
警部はノートパソコンを片手で閉じると、アンダーソンの両肩をつかんでソファに座らせ、しゃがんで人差し指をつきつけた。
「頭を冷やせ。こんなくだらん…」
「彼の遺体は解剖されなかったんですよ」
アンダーソンはむきになって言った。レストレードは口をあけたまま固まった。…言うことがおかしすぎる。どう扱ったものか。
「…なんで解剖する必要があるんだ?検死報告を読んだろ?きちんと手順を踏んでる。明らかな自殺だ。しかも大勢の目の前で飛び降りた」
とりわけジョン・ワトスンの目の前で。そう言うのをためらっていると、アンダーソンは腕を組んでフンと鼻を鳴らした。
「すぐに死亡証明が記録された。直後に」
「病院の真ん前だったからな」
「そしてすぐに埋葬された」
「ローマ法王じゃない」
「手際がよすぎますよ。警察がまったく手を出せないうちに埋葬されて…」
「必要がなかったんだ。手順は間違ってない」
警部は首を振ってため息をついた。
「とにかく今日は休んで頭を冷やせ。俺が連絡しておく。なにもするな。あのクソみたいな掲示板に書かれてることはみんなでたらめだ。ほとんどじゃない。全部だ。こんなバカなことを二度と言わせるな。わかったな?」
警部はアンダーソンの目の前で指を振って念を押すと立ち上がった。アンダーソンは目を細めて首を振りながら警部を見上げた。
「でも…何かがおかしい」
「……」
警部はまたため息をつき、デスクの前の壁を振り返った。シャーロックの死を報じた新聞や雑誌の切り抜きが貼られていた。そしてバーツ前の死亡現場の写真。生前のシャーロックの写真まで。
その光景は何かを思い出させた。奇妙なことに、それはベイカー街のあの部屋だ。彼は大がかりな事件の推理をするとき、手がかりを部屋の壁いっぱいに貼りだしていた。
だが受ける印象はまったく違う。アンダーソンの作ったコラージュは、作り手の頭のなかを映したように混沌としている。答えを求めながら、現実を拒絶して閉じている。ジョンの言ったことを思い出した。
『あれは何日も寝てない顔だ。気をつけてやれよ。シャーロックは…人の頭を混ぜっ返す奴だから』
…たしかに彼は大勢の頭を混ぜっ返している。死んだあとでさえ。
* * * * *
本人が望んでいたとは思えないが、生前のシャーロックはタブロイド紙の人気者であり、崇拝者がいた。そのため突然の死の直後から、警察の判断を疑問視する声が上がった。
タブロイド紙は両方の見方を節操なく煽り、シャーロックとつながりのあったヤードの関係者にまで、三流記者が押しかけた。ある時はシャーロックの熱烈な「ファン」の青年が、ヤードから出てきたアンダーソンの目の前に立ちはだかった。
「この人殺し!」
彼はそうののしって、アンダーソンに卵をぶつけた。
(中略)
警部はアンダーソンを見下ろした。彼とは長く一緒に仕事をしてきた。飛び抜けて優秀だとは言わないが、まじめに仕事をする。犯罪現場の保持についてのこだわりは、警部自身感服したこともあった。
総じて鼻につくところはあるものの、アンダーソンはバカではない。少なくとも警察の鑑識で働いている男だ。自己評価が高く、体面を傷つけられることを嫌い、身だしなみもおろそかにはしなかった。
ここいるアンダーソンは別人だ。しわだらけのシャツを着て無精ひげを生やし、隈に囲まれた眼ばかりが不自然にぎらぎらしている。どこか麻薬中毒患者のようにも見えた。
彼をこうしたのはシャーロックであり、その彼を今支えているのもおそらくシャーロックだ。まさに麻薬じゃないか。そして……警部はそれ以上考えるのをやめた。ジョンのこと、そして自分のしたこと、できなかったことを。悔やんでも始まらない。
「アンダーソン」
警部は見下ろしながら、小さな声で言った。半ば自分に言い聞かせるような声だった。
「誰にもおまえを責める権利はない」
アンダーソンは眉をしかめた。
「そんなことを言ってるんじゃ……」
「わかってる、わかってる」
警部はうなずいた。
「…とにかく眠って頭をすっきりさせろ。明日は仕事に戻るんだ」
警部はそう言うと、アンダーソンの肩をたたいて部屋を出ていった。
* * * * *
シャーロックが初めてスコットランドヤードに現れたときのことを、アンダーソンは覚えていた。レストレード警部に伴われてきたその青年を、アンダーソンは警部の親戚の学生だろうと思った。ヤードに憧れていて、仕事場を見せてほしいとせがんだ甥っ子か何かだと。そんなことを思わせるほど、黙って部屋を見回すシャーロックはどこか幼く見えた。
機器を見せてやってほしいと警部に言われ、アンダーソンは自尊心をくすぐられさえした。
(中略)
採取された証拠の閲覧に飽き足らず、シャーロックはレストレード警部に直接犯罪現場を見せろと要求した。警部は聞き入れ、やがては警部のほうからシャーロックを呼び出すようになった。鑑識の報告書をさしおいて、シャーロックの証拠分析が参照された。そしてそれは、いつも正しかった。シャーロックはいっさい報酬を受け取らず、自分の名前が報告書に載ることも望まなかった。
アンダーソンはますますシャーロックを嫌った。嫌っていた。あんなにいやな奴はいなかった――
* * * * *
「――こぼれてるわ」
サリー・ドノヴァン巡査部長の声がして、アンダーソンは我に返った。
「え?」
「こぼれてる」
アンダーソンが持っていた容器から、指紋採集用のアルミニウム粉末がこぼれて床に散っていた。アンダーソンは慌てて蓋をした。サリーは首をかしげて聞いた。
「…大丈夫なの?」
「もちろん、もちろん」
アンダーソンは何度もうなずいた。サリーは言いにくそうにつぶやいた。
「聞いたわ」
「え?」
サリーは肩をすくめた。
「なんでもない。まだかかる?」
「もう少し…すぐすむよ」
裏通りの古い葉巻店。店内は嵐のあとのように荒らされ、格子窓から夕陽が差し込んでいる。強盗事件の現場だった。木製のカウンターの向こうの壁には、ウィンストン・チャーチルが葉巻をくわえた写真がかしいでいた。
(中略)
サリーの声を無視して、アンダーソンは店のなかを歩き始めた。奇妙な動作で見回し、ときどき動きを止めてはまた移動する。サリーはため息をつき、腕を組んで見守った。
「――狂言だ」
「え?」
アンダーソンはサリーを振り返った。
「…これは狂言強盗だ。あきらかに」
アンダーソンは顔をほころばせ、一人でうなずいた。サリーは眉をしかめた。
「ふざけてるの?」
「…なに?」
「シャーロック・ホームズのまねなんか」
「まねなんかしてない!わかるんだ!」
アンダーソンは嬉しそうに言った。
「やめてよ!」
サリーはそう言うと、怒ったように外に出て行った。
レストレード警部は目撃者の話を聞き終えたところだった。近づいてきたサリーに気づき、手帳になにか書き込みながら聞いた。
「アンダーソンは?」
「もうすぐ終わります」
警部は声を小さくした。
「そうじゃなくて…」
「…わかりません」
警部は眉をしかめてサリーを振り返った。サリーは首を振ってもう一度言った。
「私にはもうわからない」
アンダーソンはサリーの機嫌など気にしなかった。そしてレジの周りや、チョークで足跡を囲った床を見回した。わかる。シャーロックのやっていたことがわかる。そっくりそのまま乗り移ったように理解できる。シャーロックの思考法が、今の俺にはわかる。
(後略)…
|