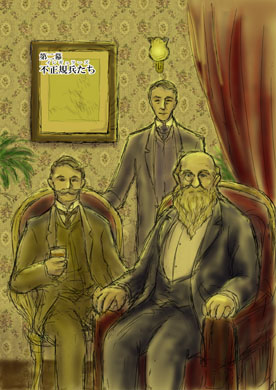プロローグ
逃亡者
真っ暗な岩砂漠に、どしゃぶりの雨が降っていた。
この一時間でとっくに例年の年間降水量を超えている。
稲妻が闇を切り裂き、荒れ狂う雷鳴が耳を麻痺させる。
巨大な遠浅の浜辺になった荒地に、一本線を引いたように未舗装の道が伸びている。その道を、泥だらけのピックアップトラックが水煙をたてて走ってくる。
ハンドルを握る境界物理学者アンドレス・フアレスは、大きな手のひらにじっとりと汗をかき、叩きつつける雨でほとんどなにも見えないフロントガラスに目をこらしていた。黒い髪が汗で額にはりついている。車はどこへ向かっているのか。どこへ向かえばいいのか。確かなのは、止まってはいけないこと。少しでも早く離れること。行くのだ。どこか安全なところへ。
「アンディ、もっと速く!」
アンドレスの肩の高さから、同僚のエネルギー物理学者フランソワ・ジェサップが甲高い声でせきたてた。亜麻色のねこっ毛に覆われた頭をふりたて、見えもしない追っ手を振り返っている。
弱冠19歳のこの天才物理学者は、見た目には小柄で華奢だが、大柄で六つ年上のアンドレスを迫力で完全に圧している。
「もっと速く走れ!」
「わ、わかってるよ!」
アンドレスはしかられた子供のように声を張り上げた。速く。安全なところへ。でも安全なところなんてあるのだろうか?
アンドレスの混乱した思考をさらにかき乱すように、雷鳴がとどろいた。フランソワの口から悪態が飛び出す。
「くそっ、畜生!なんなんだよこの天気は!え?」
…なぜ彼はいつも意識して汚い言葉を使いたがるのだろう、とアンドレスは顔をしかめた。身についてはいないのに。
そのとき、バックミラーに地面を照らすサーチライトが映りこんだ。フランソワはうしろを振り返り、反射的にアンドレスのたくましい肩をバックハンドではたいた。
「来たぞ!」
「わかってる!」
アンドレスはアクセルを踏み込んだ。視界が悪いため、猛スピードで走っているのに止まっているような錯覚に陥る。豪雨と雷でジェットヘリの爆音もほとんどかき消され、不気味にサーチライトだけが近づいてくる。シュールな悪夢のように現実感がない。
フランソワは、アンドレスが過度の緊張で運転を誤ることを恐れて、急に声をやわらげて言った。
「安心しろアンディ、俺たちは大事なものを持ってるんだ。撃てるもんか」
「…そ、そうだよね」
「絶対に大丈夫だ」
フランソワは自信に満ちた声で保証した。アンドレスは少し安心した。頭にあったのは自分のことではなく、同僚の安全だった。
だが、彼らの期待を裏切るように、バンパーをかすめて威嚇射撃が始まった。
アンドレスは触覚を抜かれた蟻のように、めちゃくちゃに車を迷走させた。
一瞬あたりが昼のように明るくなり、ドーンという轟音と振動が鼓膜と腹に伝わった。ヘリに落雷したのだ。ヘリは地面に激突し、二人の後方100メートルほどのところで爆発した。地響きがして、タイヤが宙に浮いた。 それ以上の追手はこなかった。しばらく走って、アンドレスはラジオのスイッチをいれた。激しいノイズが入るが、かろうじて聞き取れる。
『…発電所は無事です。繰り返します。これは停電ではありません。現在までに報告されているのは、すべてコンピュータデータの消失であり、送電は平常どおり行われています…』
「停電じゃなかったのか…」
アンドレスがつぶやくと、助手席のフランソワが隈の浮いた顔をあげた。
「え?」
「停電じゃないらしい。基地の中だけじゃなかったんだ」
「…そんなことがありえるか?」
フランソワは手を伸ばしてラジオの周波数を変えた。一日中カントリーミュージックを流しているローカル局までが、臨時にニュースを流している。
『さきほど、午前4時22分頃、おもなインターネットサーバーが新種のウイルスの攻撃を受けた模様です。続々とデータ消失の被害が報告されています…』
アンドレスがスイッチを何度も押しながらつぶやいた。
「カーナビがダメだ…」
「なんだと?」
フランソワが苛ついた声で聞き返した。アンドレスはあわてて続けた。
「だ、大丈夫だよ。町までは一本道だし。…どっちにしろこの車にいつまでも乗っているわけにはいかないだろ?」
「…そうだな…」
二人が奪ったピックアップトラックには、でかでかと軍用車のマークがついていた。フランソワは忌々しそうにため息をついた。
「バスか。いや、鉄道のほうが…」
ノイズ混じりのラジオが答えるように伝えた。
『…影響は鉄道、その他の交通機関、行政機関にも広がっており、大統領はさきほど非常事態宣言を…』
フランソワは舌打ちした。
「冗談じゃないぜ、こんなときに!」
「でも…」
アンドレスは遠慮がちに言った。
「おかげで助かったんじゃないか?奴らが遅かったのはきっとこのせいだ」
「…」
フランソワは不機嫌そうに鼻を鳴らし、背もたれによりかかった。
アンドレスは正しかった。二人は気づいていなかったが、軍用車にはすべて識別用の発信機がついており、追手は彼らの位置を把握できるはずだった。だがなぜかそれを検知できず、追跡者は推測と目視に頼るしかなかったのだ。
しだいに雨は小降りになった。立入禁止区域の境界にさしかかる頃には、重苦しい雲が空の向こうに吸い出されるように晴れ、しらじらと夜が明けた。
境界を見下ろす丘の上に、侵入者を監視するパトカーが見えた。じつはこれが無人であり、侵入者への視覚効果を狙った置物にすぎないことを二人は知っていた。
二人の車は境界を通り過ぎた。フランソワは振り返った。塀もバリケードもなく、見渡すかぎり誰もいない岩砂漠に、警告看板がぽつんと立っていた。こう書かれていた。
『軍事エリア 立入禁止 撮影禁止 侵入者は警告なしに射殺する』
フランソワとアンドレスは町の近くでピックアップトラックを乗り捨てた。町は静まり返っていた。通行人もいない。
ひとつしかない小さな駅に行くと、案の定鉄道は止まっているようだった。真っ暗な立体表示モニターの横に、『復旧未定』と貼り紙があった。アンドレスはあっけにとられた顔で貼り紙にさわった。
「紙だよ」
「ホロスクリーンも使えないのか?どうなってるんだ」
フランソワは閉まったガラスドアの中を覗き込んだ。せまい駅舎の中には、ペイカード読取機とベンチがひとつあるのが見えたが、人影はなかった。この小さな町では、もともと鉄道は日に数本しか来ない。
二人は町の反対側にあるバスターミナルに向かった。乗車待ちの列ができていて、さいわいバスは動いているようだった。列は、意外にもずらりと並んだペイカード読取機ではなく、ひとつしかない有人の案内窓口に続いていた。ペイカード読取機にはまた紙が貼ってあり、『使用不能』と書かれていた。
列は短いにも関わらず、なかなか進まなかった。二人のすぐ前に並んでいる老夫婦が、そのまた前の若いカップルと話し込んでいた。
「読取機の故障でしょう?」
「いや、カード自体が使えないみたいですよ」
「…じゃあどうするの?」
窓口から非難めいた声が聞こえた。
「現金だって?」
皆がいっせいにそちらを向いた。窓口係の若い男は、『俺のせいじゃない』と言わんばかりの顔で、言葉遣いだけは丁寧に説明した。
「申し訳ありませんが、ペイカードのメインコンピュータがダウンして、アクセスできないんです。復旧までは使えません。お急ぎでしたら現金で…」
「今時現金なんて持ち歩く人間がいるかよ!」
フランソワとアンドレスは顔を見合わせた。ペイカードを使っては足がつくので、二人は現金を集められるだけ持ってきていたのだ。
… |